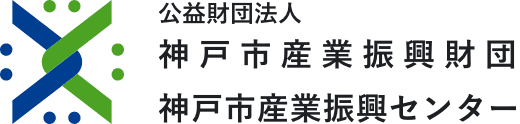兵庫運河で真珠の養殖?
子どもたちが学ぶ命と環境プロジェクト
みなさん、兵庫運河で真珠の養殖がされているってご存知でしたか?
兵庫運河・真珠貝プロジェクト
兵庫区にある兵庫運河では、親子でアコヤ貝を育てながら、生物の命の大切さや環境が及ぼす影響を学ぶ「兵庫運河・真珠貝プロジェクト」が進められています。2005~2006年に神戸市環境局が行ったアコヤ貝の育成実験を経て、2007年6月にプロジェクトが設立されました。今年で19年目に入ります。
今回は2024年に行われた、真珠貝の「移植式」から「浜揚げ式」の様子を取材していましたのでご紹介します。
2024年6月30日 移植式@和田岬小学校

挿核(そうかく)とは?
アコヤ貝をメスで小さく切開し、核とピースを入れる手術のことです。
挿核を行うアコヤ貝は生きているので、事前に麻酔をかけ口を閉じないように楔(くさび)をしておきます。
●核:淡水産二枚貝(ミシシッピードブ貝)の貝殻を球状に削り出したもの
●ピース:アコヤ貝の外套膜(がいとうまく)組織の一部
核とピースを一緒に入れることで、アコヤ貝が真珠層を形成するのだそうです。

棒状の器具を使用してアコヤ貝に核を挿核するのですが、器具の上に核がのっているだけなので、なかなか難しい作業でした。コロコロっと転がってしまいます。
本プロジェクトの協力企業である株式会社大月真珠の職人さんにお手伝いいただきながら、何とか貝の中に挿核することができました。


移植したアコヤ貝を兵庫運河に
移植したアコヤ貝を兵庫運河の上に設置されたポンツーン(浮き桟橋)から浜入れしました。
浜入れしたアコヤ貝は、挿核した際にできたキズが回復するまでしばらくの間、静かに養生させます。
運河にアコヤ貝を入れていると、カキやフジツボ、ホヤなどが付着します。
カキやフジツボなどの生物はアコヤ貝と同じエサを食べるため、そのままにするとアコヤ貝の成長を妨げてしまうのです。そのため、本プロジェクトに参加する小学生によって定期的に貝の掃除や兵庫運河の清掃を行い、約5ヶ月アコヤ貝の育成を行ないました。


2024年11月30日 浜揚げ式 @和田岬小学校
挿核したアコヤ貝を兵庫運河で約5ヶ月間育成し、いよいよ浜揚げの日。
近年の異常気象の影響により浜揚げできるアコヤ貝の数は減少しているそうですが、本プロジェクトに参加する小学生のお世話によって、2024年は430枚のアコヤ貝の育成スタートから結果として345枚のアコヤ貝を浜揚げすることができました。
また、90g以上の貝が2023年に比べて多く、58枚もあったそうです。
実際に真珠が出来ているのでしょうか?
本プロジェクトの会長である株式会社新川鉄工所の道林社長から、アコヤ貝の構造について説明を受けながら真珠ができているか確認します。



真珠が入っていると思われる外套膜部分を探していくと、出てきました!
6月に挿核したアコヤ貝からこのような綺麗な真珠ができているなんて、感動です。
他の貝も開けていくと、きれいに真珠層が巻いているものやグレーがかったもの、真珠層がなく核だけが残ったものもありました。その他にも育成段階で挿核した核を吐き出してしまった貝もあり、綺麗な真珠ができる難しさを感じました。
アコヤ貝から取り出した真珠は、本プロジェクトの協力企業である株式会社大月真珠が綺麗に洗浄します。

最後に
「兵庫運河・真珠貝プロジェクト」は、アコヤ貝から真珠を取り出すことが目的ではありません。
アコヤ貝の育成活動を通じて、子どもたちに環境を守ることの大切さや生物の命の尊さを感じ学んで欲しいという長年の思いが受け継がれています。
そして2025年は、運河の環境をもっと良くするために、水質をきれいにする機械(マイクロバブル発生器)の導入を目指して活動しています。これは運河の底の状態(底質)を改善し、アコヤ貝たちがより元気に育つような環境をつくるための取り組みです。現在は導入のために必要な手続きを進めており、6月末の移植式までの設置を目標にしています。
今後の活動の様子や、新しい取り組みについても、このブログで紹介していく予定です。
ぜひ、これからも注目してみてください!